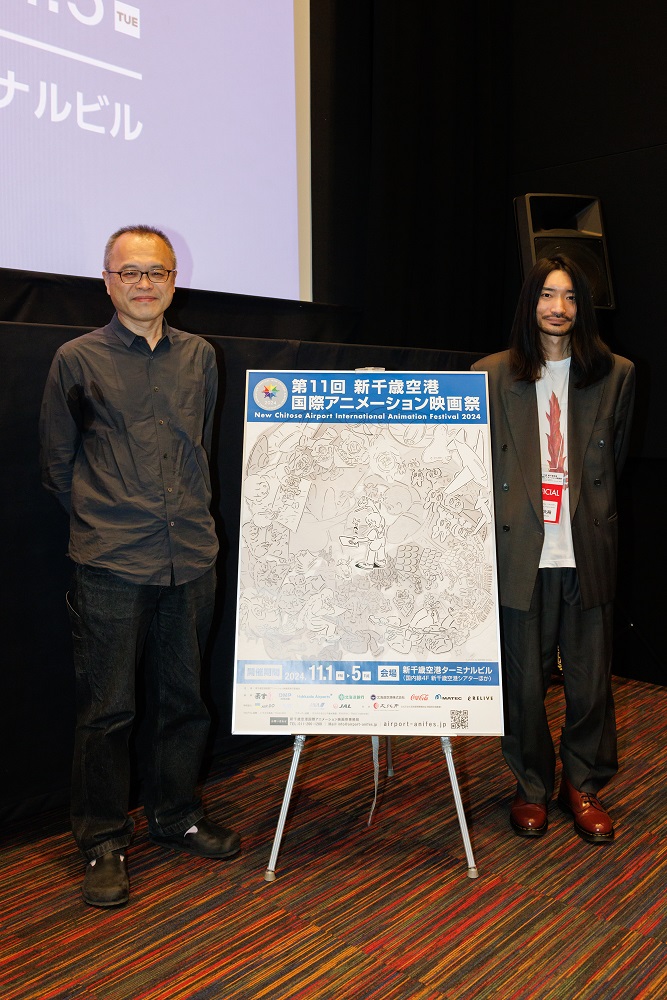NEWS
 2024年11月1日(金)〜5日(火)に開催された「第11回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月4日(月・祝)には、コンペティション長編部門入選作品であり、長編部門審査員特別賞を受賞した『ルックバック』について、「メイキングオブ:ルックバック」と題し、監督である押山清高氏を迎えて本作の制作背景についてお話いただきました。聞き手は本映画祭委員の田中大裕です。
2024年11月1日(金)〜5日(火)に開催された「第11回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」。11月4日(月・祝)には、コンペティション長編部門入選作品であり、長編部門審査員特別賞を受賞した『ルックバック』について、「メイキングオブ:ルックバック」と題し、監督である押山清高氏を迎えて本作の制作背景についてお話いただきました。聞き手は本映画祭委員の田中大裕です。メイキングオブ:ルックバック
https://airport-anifes.jp/programs/mo_look_back/
複数回映画館に足を運ぶ観客も多く、興行収入20億円を突破しロングヒットを記録した『ルックバック』は、現在Amazonプライムでの配信もスタート。公開から3~4ヶ月を経過してもなお、押山監督には問い合わせや取材が殺到しており、多忙な日々が続いています。
本作はアヌシー国際アニメーション映画祭を皮切りに、ロサンゼルスやソウルをはじめ世界各地で上映されており、中国では驚異の5000館超で公開されました。「一般の方々やアニメーション関係者から非常に好評なリアクションをいただいている」と喜びを語りました。

漫画をアニメーションに落とし込んでいくこと
今回、キャラクターデザインも担当された押山監督。藤本タツキさんの原作をアニメーションにする際に特に注意を払った点について触れ、「藤本タツキさんの絵はタッチが多く密度の高い絵が特徴」とし、それをアニメーションに落とし込んでいくときに、「線の密度をどのように調整するかを考えました」と、キャラクターデザインを見せながら説明していきます。
例えば、京本の目の表現について「涙袋なのか、下まつ毛なのか、くまなのか」といった細部を明確化するなど、制作チームが統一して描けるように整理したプロセスについて解説。
また、絵コンテ等にいつまでも決定稿が出てきていないことについて田中に指摘されると、「優柔不断さのせいです」と笑いつつ、「描き直したいときには描き直せるように」決めないことにしていたと明かします。 60分弱の本作でも、絵コンテ完成からアニメーターと制作を開始し完成するまで1年ほど描き続けることになるアニメーション制作の現場。「作品への理解が進むことで絵柄はどうしても変わってきてしまう。デザインにも自由度を持たせた方が良い表現を追求することで結果よいものになると思っています」と制作の裏側についても振り返りました。

さらに原作をアニメーション化するにあたっての藤本タツキ先生とのやりとりについては「原作を最大限尊重し映像化することを最初に伝えた」と話したと明かしました。そうした原作への思いは、一本の線に仕上げすぎない表現手法や、輪郭を明確にしない瞳の描き方など、通常のアニメーションでは使用しない表現に挑戦していることなどへの話の中に現れていました。
また漫画と映像の違いとして、漫画の表現として自由にコマ割りができること、映像では必ず横長のサイズで観せる必要があること、空間としての人物の立ち位置、動きでより加えることによってドラマが魅力的に見えるかなどを挙げ、漫画表現をアニメーションにする上で、漫画の印象をそのまま踏襲すること意識したと強調しました。
音があることが、漫画との大きな違い
田中は、ナチュラルな芝居がアニメ関係者の中でも話題になっていたことに触れ、「どのようにそう作っていったのか」と質問すると、「オーディションの中で自然な声が出せる、ナチュラルな芝居ができる人を選んだ」と述べ、演技について特別な指示はなかったと答えました。「結果的に声優ではなくて実写の俳優を選んだことになるので、作品全体がキャラクターと馴染んだと思う」と回顧しました。
また音楽については、「絵コンテ(アニメ映画の設計図)の段階でビデオコンテを作って、自分でセリフや欲しいイメージの音楽を入れ込んで見せた」と音楽を担当したharuka nakamura氏との制作プロセスを回想し、「何を欲しているのか掴んでもらったあとは、自由に作ってもらった」と押山監督。

映り込み、光の表現、絵画のように描いていきたい
冒頭、主人公が机に向かう姿と机に置いてある鏡に映り込む表情の表現は大変印象的でした。映像へのこだわりとして、「反射というものを大事に描いているのでは」と田中からの質問に、押山監督は「作品の中で映り込みを積極的に描いていこうと決めていた」と言い、「物の反射光など、背景美術のみなさんには意識してもらった」と印象的な映り込みが描かれるシーンを見せながら解説しました。
アニメーションで映り込みを描くということは、さらに別で映り込みだけの絵を用意することになるのだそう。「アニメーターから上がってきたレイアウトに対して(映り込みの指示等を足して)どんどん大変にしていった。申し訳ない」と苦笑いしつつ「映り込みが好きなんです」とそのこだわりについてさらに話は深まっていきます。
押山監督は、アニメーションの現場にある課題として、背景美術は効率化を求められるあまり、絵として描いているという意識が薄れてしまいがちであるということを指摘し「出来るだけ一枚絵として美しい絵にしてほしい」と注文をしていたと明かします。
また押山監督が印象派の作品が好きであったのと、藤本タツキさんが学生時代に油絵学科だったことから、水彩的な背景ではなく、厚塗りでしっかり色が乗っている絵画的な表現になっていったと振り返りました。
これに対して田中は、「映り込みや光の表現というのは、絵画の歴史としても繰り返されてきたこと。光をどうやってアニメーションに取り込むかっていうことに熱を入れて取り組んでいると感じました」と述べ、トークを締めくくりました。
「ルックバック」はPrime Videoでの世界配信中!詳細はルックバック公式サイトをご覧ください。


2024年11月1日(金)〜5日(火)に開催された「第11回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」。その一環として、コンペティション長編部門入選作品『化け猫あんずちゃん』の制作背景を紹介する「メイキングオブ:化け猫あんずちゃん」が行われました。トークには監督の久野遥子氏、山下敦弘氏、プロデューサーの近藤慶一氏が登壇し、作品制作の裏側に迫るエピソードが語られました。
11月15日からの北米での劇場公開を目前に控えていた今回、英語吹き替え版での予告編を視聴し、トークをスタートしました。
メイキングオブ:化け猫あんずちゃん
https://airport-anifes.jp/programs/mo_ghost_cat_anzu/
映画祭での出会いからはじまった物語
『化け猫あんずちゃん』が日本とフランスの共同制作となるきっかけは2018年、新千歳空港国際アニメーション映画祭での出会いでした。当時の映画祭メインビジュアルを手がけた久野監督が、コンペティション長編部門の審査員で来日していたフランスを代表するアニメーションスタジオ「Miyu Productions」のエマニュエル氏に声をかけられたことから、共同制作のアイデアが形になったといいます。
近藤プロデューサーは、「私たちが愛してやまないこの映画祭で皆さんに完成作品を披露できるということが本当に嬉しく、感慨深い思いです。また新千歳空港の温泉に入って一杯やりたいです」とMiyu Productionsのエマニュエルさんとピエールさんからのメッセージを読み上げると、会場からの温かい拍手で包まれました。
そのときの出会いについて、久野さんは「エマニュエルさんが初めて声をかけてくれたとき、そのキラキラした目が印象的でした」と当時を懐かしそうに振り返りました。

「ロトスコープ」により制作された本作と共同監督という体制について
本作の特徴的な制作手法として採用された「ロトスコープ」は、実写映像をトレースしてアニメーション化する技法です。実写撮影には、あんずちゃん役に森山未來ほか、青木崇高、市川実和子、鈴木慶一など実力派俳優が参加。アニメーション制作に先立ち、ほぼ一本の実写映画が撮影されたと言っても過言ではありません。
実写監督を務めた山下さんは、ロトスコープの手法について事前に説明を受けた上で制作を開始し、芝居や演出に関しては久野さんと綿密に相談しながら進めたと語りました。
アニメーションだけで作られたのは全部3割ぐらいで、それ以外は実写を基にアニメーションが作られていると話し、「極力音声も、実写撮影で収録したものをアニメーションにも使うというのが、この作品の大事なポイントだった」とも近藤さんが明かしました。
さらに制作過程でアニメーションになっていくプロセスが興味深かったと話す山下さん。これに対し、近藤さんから「実写の印象を損なわずに森山さんを猫にするっていうのがとても難しい」と、実際に俳優陣による実写映像とアニメーションの比較映像も見せてもらい解説してくれました。それぞれの実写での素材からアニメーションとして表現する際に作られた、キャラクターデザインも、俳優さんの表情や動き、衣装などもかなり忠実に再現しつつアニメーションとしてデフォルメされている様子に、その紹介では会場から笑い声も起こりました。
久野さんは「アニメーション作家は一生懸命頭の中で動きを考えていく、動かしていく」ものであることと話しつつ、「お芝居のプロが出してくるものの面白さ、環境と役者同士の関わり合いで生まれる偶然性など、頭の中では起きないことがたくさんあって、なんて豊かで大変なことだった」と強調し、その挑戦の過程を明かしました。
これについて、役者の小さなお芝居がきちんとアニメーションとして残っていることを指摘された久野さんは「お芝居が良いからこそ、お芝居が良いからこそ、どうやってアニメらしいメリハリをつけるかというのが難しかった」とロトスコープならではの悩みについても打ち明けました。

左からプロデューサーの近藤慶一氏、監督である山下敦弘氏と久野遥子氏
日仏合作が見せてくれた豊かさ
Miyu Productionsが参加する3〜4年前から、日本チームだけでシナリオを進めていたという本作。「MIYUが参加してからは、フランスからの意見を取り入れながら結構変わっていったという印象」と話す山下さんに、久野さんは「例えば、妖怪や地獄、温泉みたいな日本ならではの要素を面白がって、結果的にはそこの要素を少し増やそうかみたいな感じになった」と言います。
今回の日仏分業体制で行われ、日本側で原画・動画といったアニメーションの制作が行われつつ、フランス側では背景美術・色彩設計を手掛けました。
「フランスのスタッフは、作家性が強い方たちが多い印象で、たくさんのアイデアを持ってきてくれた」と久野さん。美術背景を担当するジュリアンさんは、原作を読んで印象派のボナールという作家のイメージを参考として提示してきてくれたと明かします。
まずはジュリアンさんと久野さんで、実写映像から重要そうなカットを選んで、そこから”カラーボード”を作り、日本でレイアウトを、フランスで線画と色をつけていくという役割だったと言います。
「ジュリアンさんたちじゃなきゃ描けないカットがたくさんある」と印象的なシーンを振り返り、文化の違いや宗教的な感覚によるアウトプットの違いが豊かさに繋がったそうです。

「化け猫あんずちゃん」が示す協働による価値
また合作の利点について近藤さんから問われて「作品の豊かさ」を挙げた山下さん。「日本人が見た日本の風景ではないものをフランスチーム、ジュリアンさんが作ってくれた。やっぱ違う厚みが出たかなとはすごく思った。すごく噛み合った」と。久野さんは「MIYUのチームの作品ファーストの姿勢はすごい。狭くなった視野を広げてくれた、盛り上げてくれた」と日仏合作の意義を力強く語ります。
山下さんは、「世界中で上映されるアニメーションのすごさ、アニメの力を感じた。ロトスコープの経験を次に繋げたい」と制作を振り返り自身の思いを述べました。
近藤さんは、「この映画は10年前に僕が企画したんですけども」と、なかなか制作段階に進めることが出来ない中で、原作・シナリオの良さ、試みの面白さを評価して手を上げてくれたのがMiyu Productionsであったことを振り返り、「売り上げがをどうこうではなく、面白い映画を作るためにどうすれば良いかを皆さんで考えた映画だった。何か問題が起きてもみんなで考えられたから面白い映画づくりができたと思う。」と締めくくりました。
本映画祭におけるこれ以上ない国際的なコラボレーションの実現に感謝を込めながら、さらなるアニメーション文化の発展を目指す意欲が高まるトークイベントとなりました。
映画『化け猫あんずちゃん』公式サイト
https://ghostcat-anzu.jp/

2024年11月4日の『Glass House』上映終了後に行われたトークプログラム〈「方法」からアニメーションの文法を再考する〉では、本映画祭委員である田中大裕氏を聞き手に、アニメーション作家の山村 浩二 氏とトークを行いました。
以下はそのトークの様子を書き起こしたものです。

田中:まずは、本作を観た率直な感想をお聞かせください。
山村: トークをするということで、事前にテレビモニターで一度プレビューさせていただきましたが、皆さんと一緒に大画面で観てみて、一人でプレビューしたときよりもさらに面白く感じました。睡魔に襲われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは意図的だと思います。催眠的な音楽と映像もあり、白黒ながらもサイケデリックで、20世紀のさまざまな芸術の引用が端々に見えて、まるで20世紀から未来を見たようなレトロフューチャーな印象を受けました。
各章にタイトルがついていますが、全体としては「ガラスのバベルの塔」というのが一つの大きなモチーフになっていて、そのバベルの塔が最後、崩壊するという形で終わっています。バベルの塔は人間のある種の英知のおごりで、天にも届く塔を作ろうとして神の怒りを買い、壊されるという旧約聖書の神話ですが、バベルそのものを我々の現代の英知に置き換えたような設定の映画かなというふうに捉えました。
田中:本作は、一般的には非物語的な作品と見なされうるように思われます。しかしながら、山村さんは本作に物語性を見出しているようですね。本作の物語について、山村さんなりの解釈をお聞かせください。
山村:初見は非常に抽象度が高い作品だと思いましたが、2度目の鑑賞では、章ごとのタイトルが物語性を持って構築されていることに気付きました。セリフはなく、登場する人物や鳥などの具象的な事物もやや半抽象的に表現されていますが、作品の中から読み取れる様々な引用やヒントを繋げていくことで、ちゃんと物語になることがわかりました。
僕が読み取った大まかなストーリーは、ガラスのバベルの塔に閉じ込められ、人間性を失っていった人類が塔によってハイパーコネクテッド、ネットなどを介しての複雑な繋がりを持つものの、最終的にそれがバラバラにされるというものでした。バベルの塔の伝説も同様に、塔の崩壊によって言語が世界中に散らばり、私たちのコミュニケーションが困難になったという神話です。要するに、ディスコミュニケーションが大きなストーリーの流れになっていると感じます。
ボリス・ラべの類いまれなグラフィックのセンスは言うまでもありませんが、本作はもともと、アルゼンチンの現代作曲家ルーカス・ファギンが作曲した音楽に基づいており、演奏会のバックで流す映像として作られたものだそうです。実際のライブコンサート版を観た方が楽しめる可能性は高いと思いますが、この長編版のほかに、コンパクトにまとめた短編版もあると聞いています。
ストーリーに関しては、各楽曲をルーカス・ファギンが作り、9つある章のタイトルも恐らく音楽のタイトルに由来しているのではないかと想像します。制作の成り立ちから考えると、ボリス・ラべが音楽のコンセプトに沿ったビジュアルイメージを作り上げていったのではないかと思います。
ボリス・ラべのWebサイトには、ルーカス・ファギンの音楽のインスピレーションとして、リゲティの室内楽団、ピンク・フロイドのアルバム『The Dark Side of The Moon』の収録曲「On the Run」、ヴィクトル・ヴァザルリの睡眠絵画が挙げられていて、この三つが全体のビジュアルにも大きな影響を与えていると考えられます。
田中:我々が山村さんにトークを依頼をした際、返ってきた言葉が「紹介文を読むよりもわかりやすい作品だった」というものでした。思うに本作を難解にしているのは、作品それ自体の構造というよりも、「ナラティブ/ノンナラティブ」という二項対立を前提に作品を鑑賞してしまう先入観が理由かもしれません。
山村:オタワ国際アニメーション映画祭でも「ナラティブ」と「ノンナラティブ」の2つにカテゴリー分けしていますが、これは物語が読み取りやすいものをナラティブ、実験的な作品をノンナラティブとして分けているだけで、僕は多くのノンナラティブ作品にも物語性があると思います。マックス・ハトラーの光学録音の発想に基づいた作品のように、20世紀の絶対映画の流れを汲んだ、もともと抽象的な音楽性を映画に取り入れたような作品を除けば、純粋なノンナラティブ作品は少ないのではないかと思います。
田中:そもそも長編アニメーションは劇映画、すなわちリニアな物語を前提とするものという先入観は、作り手/観客を問わず、未だ根強いように思われます。しかし、必ずしもリニアな物語は長編アニメーションの必要条件ではない。それは、山村さんの長編アニメーション『幾多の北』を観ても明らかです。
山村: 長年培われてきた映画の構造は、3部構成になっていたり、ターニングポイントがあったりと大体似たようなもので、アニメーション映画もそれに倣っているものが多いです。しかし、僕は長編アニメーションにおいて、構造の部分でこれまでのナラティブなパターンから抜け出す可能性があると考えています。
『Glass House』は9つの章に分かれていて、音楽でいう組曲のような形です。各章にタイトルがつけられ、それぞれが独立しているものと関連し合い、観客がその9つの章を繋ぎ合わせることで、1つの物語が見えてくるという構造です。一般的な映画の場合は、約15分の単位で1つの章がまとまり、それが3部構成で6パターンくらいの章が重なると長編映画になることがほとんどです。本作は40分なので長編と呼べるかどうかはわかりませんが、組曲的な9つの章から成り立つという点でその構造は非常に面白いと感じます。例えば、2フレーム単位で1つの絵があり、サブリミナルが永遠に続く2時間の映画なども面白いだろうと思います。
実は現在、1分の物語を90本繋げて90分の映画を作るという長編シナリオに取り組んでいます。この映画では、90本のショートフィルムは一見全く脈絡がないように感じられますが、それらを繋げることで何かが見えるかもしれない。このような構造における実験を試みたいと思っています。
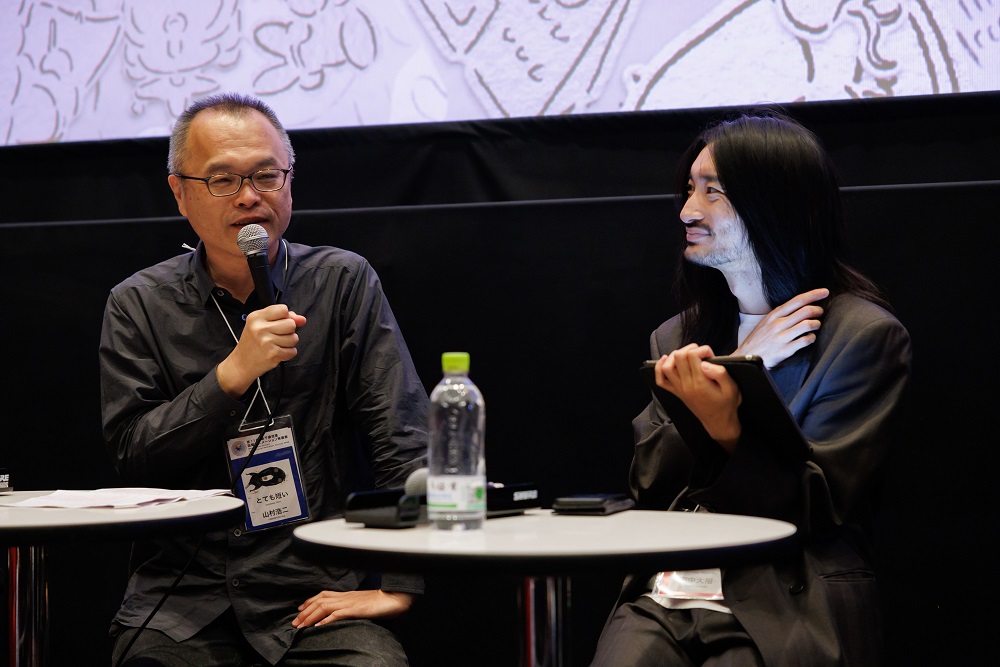
田中:本作はAI生成イメージとハンドドローイングのハイブリッド作品です。その点も評価が分かれるポイントかと思います。山村さんは「ひろしまアニメーションシーズン(HAS)」のアーティスティックディレクターとして上映作品の選考も行なっていますが、そこでは生成AIを導入した作品も選ばれていましたね。生成AIに対する山村さんの考えを教えてください。
山村:この作品は恐らく、CGIが使われていたり、マイブリッジのソースが見える写真があったり、何かの映画をベースにしてAIで加工したショットも使われていたり、様々な技法をハイブリッドした作品だと思います。AIは異なる要素を混ぜて新たなイメージや動きを作り出すことに非常に長けており、自分自身の素材をそこに加えることで、オリジナリティを生み出すための道具になるのではないかと感じています。
HASの選考でも、明らかにAIを使っている作品を2本選びました。AIが使われている作品は現代のアニメーションにおける通過点として重要だと思い選考に入れましたが、審査員の方々はあまり評価していないように感じました。「こんなの2分で作れるよね」といった反応があり、手作業を尊重しすぎる傾向があるのを感じました。
ボリス・ラべの『Rhizome』という作品が文化庁メディア芸術祭に応募された際にも、私は審査員を務めていたのですが、その時の審査会では誰一人としてこの作品に触れなかったんです。恐らく、コンピュータで簡単に作られたものだろうという印象を持っていたのでしょう。しかし、全部手書きの素材で制作されていることを僕が説明すると評価が一変し、その作品が大賞を受賞することになりました。今後生成AIについて考えていくにあたっても、アニメーション業界にある「手作りがすごい」という価値観は払拭したいと個人的には思っています。

田中:どれだけ手を動かしたかだけでアニメーションを評価すべきでないとしたら、では作品を評価するにあたって、いったい何が問われるべきだと思われますか?
山村: これは本当に難しい問題ですが、アーティストがどのような視点で、どのような試みをしようとしているのか、そしてそこに新しい発見がある作品が面白いと思います。特に映画祭という場では、既存の技術を使ったウェルメイドな作品を高く評価するよりも、私はもう少し外れた次の可能性を感じさせる作品を見つけたいし、評価したい。自分の価値観では追いつけないような作品に面白さを感じます。
田中:本作における生成AIの使われ方を、どうご覧になりましたか?
山村:本作で一番重要なモチーフになっているガラスの質感、フィクションの中での光の屈折を表現するためにAIが活用されています。また、この映画自体が引用の嵐であり、素材自体も引用が多いため、それらをスムーズにつなげる道具としてAIは最適だったと思います。ボリス・ラべは、アニメーション的な考え方を持っています。アニメーションが中割りや異なるイメージを繋ぐ力を持つのと同様に、AIもメタモルフォーゼとして異なるイメージを滑らかに繋げていくことが得意です。世の中にあるAI映像もモーフィング、つまり形が変化していくものが多く、それはアニメーションの黎明期に似ていると感じています。
田中:生成AIを含め、アニメーションにおける手法というのは「個別言語」に近いように感じます。それぞれの手法には固有の文法(syntax)があり、その範囲内でアーティストは独自の文体を練り上げていく。そういうふうにアニメーションという芸術を図式化できるかもしれないと思う時があります。山村さんはどう思いますか?
山村: その質問に100%同意できない部分もありつつ、逆に田中さんの意図をお聞きしたいところです。syntaxという部分で言うと、アニメーションは絵を動かすために非常に多くの方法が試されてきました。アニメーション技法は、動きをビジュアル上で作るための創意工夫の中から生まれてきたものであり、僕にとってはそれぞれが一種の「方言」のようなものに感じられます。例えば、切り紙っぽい方言があったり、AIっぽい方言があったりというように。
田中:それは、山村さんのアニメーションへの向き合い方が異質だからな気もします。おそらくボリス・ラべもそうですね。どういうことかというと、山村さんもボリス・ラべも様々な手法に取り組まれていますが、一般的にアニメーションのアーティストというのは、ストップモーションやハンドドローイング、コラージュなど、それぞれにシグネチャーな手法を有しているように思います。したがって手法は単なる「方言」のレベルにとどまらず、むしろ、アーティストにとって決定的な枠組みなのではないかと。
山村: 確かに、僕もボリス・ラべも同じような考えを持っていると思いますが、作品ごとに目指すものがあって、それに適した手法や物語構造をゼロから考えがちなタイプなので、ピンとこないのかもしれませんね。アニメーションの場合は非常に職人的な要素が強く、切り紙なら切り紙を一生追求しなければ極めることはできませんし、ハンドドローイングも同様に一生追求していかないと一定のレベルには到達しないという考え方があります。そうなると、一人で多くの技法を開発していくのは難しく、さらに現代ではAIが登場したことで、プログラミングのスキルがなければオリジナルの作品にはたどり着けない。工学的な発想を持たなければ、現代におけるオリジナルな文体を作れない時代に差し掛かっているかなと思います。
田中:少しズレるかもしれませんが、ソフトウェアやツールも表現をある種、言語のように規定しているように感じる時があります。
山村:その点にはとても共感します。選考で何千本ものフィルムを見ていると、あるソフトウェアが流通すると、そのソフトウェアの癖に合わせた作品が山ほど作られるようになり、それを抜ける作品が少ない。観る側としては、「もう少し工夫できないかな」とげんなりしてしまうんですよね。もちろん良い面もあって、例えばDragonframeの普及で、以前は職人にしかできなかった立体作品が、かなり多くの人がスムーズに制作できるようになってストップモーションが活性化し、手描きに必要だった難しいブラシのテクニックがアプリケーションによって補強・補助されるようになりました。ただ、作品のテイストがどれも似通ってしまう部分があり、違う使い方ができないものかともどかしい感じがします。
田中:例えば、絵画における平面性や彫刻における量感を追求する純粋化のベクトルがありますよね? 同じように手法やソフトウェア、ツールの限界を追求することが、アニメーション芸術の純粋化と考えることができるかもしれません。
山村:アニメーション自体が持つ問題だと思うんですが、アートフォームとしてのアニメーションの考え方もあれば、映画の一ジャンルとして、技法としてのアニメーションという考え方もあります。当然多くのアニメーションはエンターテイメントや娯楽、実用のために作られることが多いですよね。アートフォームとしてアニメーションの純粋さを追求するようなアーティストは限られており、実際、多くのアニメーションは産業、または工芸としての追求の方向に傾いてしまいます。
田中さんがおっしゃっている、純粋な芸術性としてのアニメーションの話は理解できますし、僕自身もアニメーションの本質や、他のメディアにはないアニメーションの純粋な形を追求したいと感じています。その可能性がどこかの作家や技術によって見つかるかもしれません。マクラーレンがカメラを使わずにフィルムに絵を描いたように、アニメーションにおける内的なイメージをどう映像としてビジュアル化するか。その過程で新しい技法や発想が生まれ、それがアニメーションの純粋な形として成り立つ可能性もあるのではないかと思います。
田中:「アニメーション」という言葉の中にはジャンルと芸術形式という似て非なる意味が共存しているということですね。言い換えれば、アニメーションにはある種の不純性がつきまとっている。山村さんやボリス・ラべは、アニメーションの不純さを前提としたうえで、それでもなお、創意工夫しながらアニメーションの純粋性を探求しているアーティストと言えるかもしれないですね。
山村:大変光栄な言葉で、ありがたいと思います。
田中:ところで今思い出したのですが、山村さんはかつて「Animations」というコレクティブを運営していましたが、その「Animations」の座談会で、細部は違うかもしれないのですが、「本当の意味でのクリエーションをCGで行うためにはプログラミングからやらないといけない」という旨の発言をされていたと記憶しています(編集者注:当該座談会は以下。「ライアン・ラーキンと『ライアン』 Animations座談会(前編)」(2007)。当トークイベントの内容をより深く理解するための補助線として参照されたい。座談会からすでに15年以上経過しているため、各参加者の考え方も当時とは変化していると推察されるが、生成AIの急速な拡大を受け、「アニメーションの本質」が再び問い直されている現在、ここで行われているCGに関する議論は、アニメーションとデジタル技術の関係を再考するうえで有益な示唆を与えてくれる)。今日の議論に通じる論点だと思います。
山村:そうですね。今後はプログラミングができないと新しい創作に向かえない時代になったかなと思います。僕がCGに手を出しづらいのは、自分でプログラミングができれば思い通りのものを作れると思うのですが、既存のアプリケーションを使って作ったものには満足できない部分があるからです。最近、初めてVRの制作をした際にCGを使いましたが、その不自由さを強く実感しました。
田中:このトークのテーマは「手法から考える」でしたが、むしろ、「文法を考える」という方が山村さんのアニメーション観に近いかもしれませんね。
山村:順番としては、そういうことだと思います。僕の場合、構造やナラティブの方法、文法への興味があって、そこへの実験性を求めています。具体的なものが決まった後に、アニメーションの手法やスタイルを探るという流れです。アニメーション制作や絵本制作においても、テキストやストーリーごとに道具や手法を変えるという方法を取ってきました。別に意図的にやっているわけではなくて、自然にそうなってしまう部分もありますが、順番としては手法や技法が後からついてくる感じですね。
田中:些細な点で恐縮ですが、「意図的にやっていない」というのは、無意識ということなのか、それとも意図することそれ自体が身体化したような感覚なのか、どちらなのでしょうか?
山村:その中間的な感じですね。僕はインスピレーション型の人間で、いきなりアイディアを思いついて何かを作りたくなる。モチベーションが急に上がって、それがどんな方法でどううまくいくのかもわからないまま創作が始まる。それが意識化されているのか無意識化されているのかで言うと、無意識化の方が近いと思います。直感型で、熟考型ではないんです。最近、脳科学の本をよく読んでいるのですが、直感というのは本質を見抜く力があるんですね。何万種類ある植物の中から、昔は科学的な方法がなくても「この草が病気に効く」といったことを勘で見つけてきて、最近科学が発展してようやくその薬の意味がわかるというようなことがあります。創作の中でも、そういった本質をつかむ直感力が非常に重要だと思います。その後に少しずつ考え始めて実行して、意識化することで必要なものがわかってきます。

田中:先程も少し話題に出ましたが、山村さんは最近ではVRにも取り組まれていますね。新しい技術は山村さんにインスピレーションを与え続けてくれますか?
山村:VRの作品を作った際、アニメーションの「見えていない部分」が見えたんですね。VRはフレームがなくて、360度が映像になります。フレームは元々カメラから来ていて、世界を切り取るものですが、実際にはフレームの外にも世界が広がっています。イマジネーションの世界にはフレームがないわけで、VRの方がより純粋なアニメーションに近いかもしれませんね。
また、モンタージュも使いづらいですね。360度の世界が急に変わってしまうので、映画的なモンタージュで文法を語る映像表現が難しくなります。アニメーションが当たり前のようにカット割りをしているのは、やっぱり映画的な文法に従っているからなんですね。改めてそのことに気づいたりもしました。
以前からモンタージュは比較的避けていて、ワンシーン・ワンカットで流れるような作品は『サティの「パラード」』からです。そして、今回『とても短い』では非常に短いワンショットで描き続けるという、映画的なカメラから抜け出したアニメーションの可能性に、VR作品の制作を経験して初めて気づき、それを言語化できるようになったという感じです。
田中:アニメーション映画祭は今後、新しい技術といかに向き合っていくべきだと思われますか?
山村:アニメーションフェスティバルと名乗っている限り、アニメーションから外れる作品をどう考えるかは、やはり問題になると思うんですね。映画祭だったら何でもありという部分もありますが、カテゴリーが限られたフェスティバルだからこそ、アニメーションとは何かを常に考え、アニメーションの可能性を見つけていけるのだと思います。実際に、HASでは「これはアニメーションではないな」と思うような、完全に実写的なAIによる作品もありました。そのような作品をどう考えるのかを常に問題提起し続けることが映画祭の役割だと思います。そして、その答えは観客の中にあると思います。
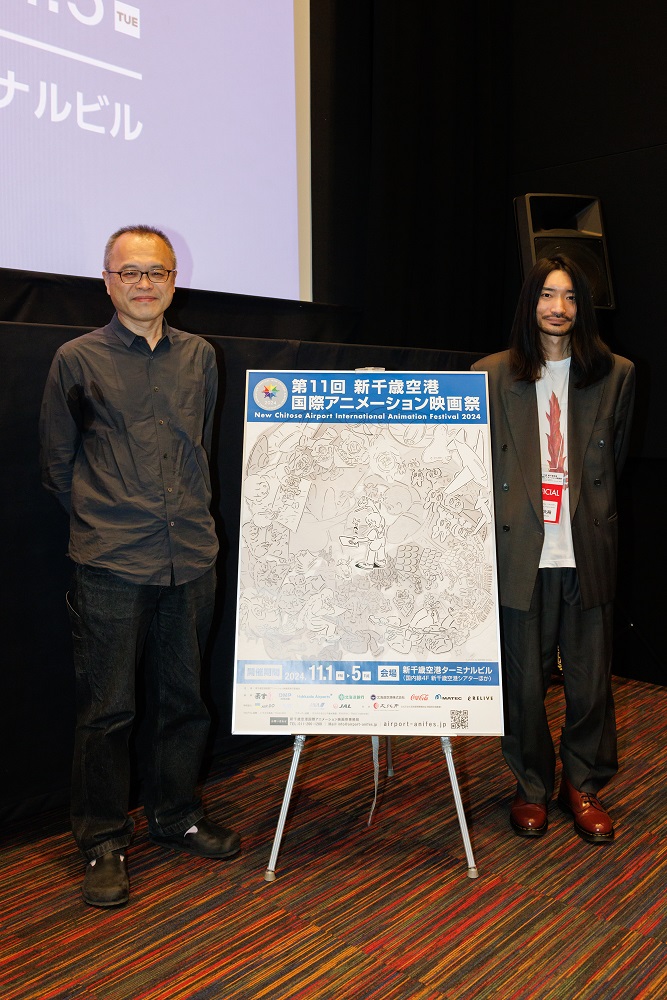
以下はそのトークの様子を書き起こしたものです。

田中:まずは、本作を観た率直な感想をお聞かせください。
山村: トークをするということで、事前にテレビモニターで一度プレビューさせていただきましたが、皆さんと一緒に大画面で観てみて、一人でプレビューしたときよりもさらに面白く感じました。睡魔に襲われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは意図的だと思います。催眠的な音楽と映像もあり、白黒ながらもサイケデリックで、20世紀のさまざまな芸術の引用が端々に見えて、まるで20世紀から未来を見たようなレトロフューチャーな印象を受けました。
各章にタイトルがついていますが、全体としては「ガラスのバベルの塔」というのが一つの大きなモチーフになっていて、そのバベルの塔が最後、崩壊するという形で終わっています。バベルの塔は人間のある種の英知のおごりで、天にも届く塔を作ろうとして神の怒りを買い、壊されるという旧約聖書の神話ですが、バベルそのものを我々の現代の英知に置き換えたような設定の映画かなというふうに捉えました。
田中:本作は、一般的には非物語的な作品と見なされうるように思われます。しかしながら、山村さんは本作に物語性を見出しているようですね。本作の物語について、山村さんなりの解釈をお聞かせください。
山村:初見は非常に抽象度が高い作品だと思いましたが、2度目の鑑賞では、章ごとのタイトルが物語性を持って構築されていることに気付きました。セリフはなく、登場する人物や鳥などの具象的な事物もやや半抽象的に表現されていますが、作品の中から読み取れる様々な引用やヒントを繋げていくことで、ちゃんと物語になることがわかりました。
僕が読み取った大まかなストーリーは、ガラスのバベルの塔に閉じ込められ、人間性を失っていった人類が塔によってハイパーコネクテッド、ネットなどを介しての複雑な繋がりを持つものの、最終的にそれがバラバラにされるというものでした。バベルの塔の伝説も同様に、塔の崩壊によって言語が世界中に散らばり、私たちのコミュニケーションが困難になったという神話です。要するに、ディスコミュニケーションが大きなストーリーの流れになっていると感じます。
ボリス・ラべの類いまれなグラフィックのセンスは言うまでもありませんが、本作はもともと、アルゼンチンの現代作曲家ルーカス・ファギンが作曲した音楽に基づいており、演奏会のバックで流す映像として作られたものだそうです。実際のライブコンサート版を観た方が楽しめる可能性は高いと思いますが、この長編版のほかに、コンパクトにまとめた短編版もあると聞いています。
ストーリーに関しては、各楽曲をルーカス・ファギンが作り、9つある章のタイトルも恐らく音楽のタイトルに由来しているのではないかと想像します。制作の成り立ちから考えると、ボリス・ラべが音楽のコンセプトに沿ったビジュアルイメージを作り上げていったのではないかと思います。
ボリス・ラべのWebサイトには、ルーカス・ファギンの音楽のインスピレーションとして、リゲティの室内楽団、ピンク・フロイドのアルバム『The Dark Side of The Moon』の収録曲「On the Run」、ヴィクトル・ヴァザルリの睡眠絵画が挙げられていて、この三つが全体のビジュアルにも大きな影響を与えていると考えられます。
田中:我々が山村さんにトークを依頼をした際、返ってきた言葉が「紹介文を読むよりもわかりやすい作品だった」というものでした。思うに本作を難解にしているのは、作品それ自体の構造というよりも、「ナラティブ/ノンナラティブ」という二項対立を前提に作品を鑑賞してしまう先入観が理由かもしれません。
山村:オタワ国際アニメーション映画祭でも「ナラティブ」と「ノンナラティブ」の2つにカテゴリー分けしていますが、これは物語が読み取りやすいものをナラティブ、実験的な作品をノンナラティブとして分けているだけで、僕は多くのノンナラティブ作品にも物語性があると思います。マックス・ハトラーの光学録音の発想に基づいた作品のように、20世紀の絶対映画の流れを汲んだ、もともと抽象的な音楽性を映画に取り入れたような作品を除けば、純粋なノンナラティブ作品は少ないのではないかと思います。
田中:そもそも長編アニメーションは劇映画、すなわちリニアな物語を前提とするものという先入観は、作り手/観客を問わず、未だ根強いように思われます。しかし、必ずしもリニアな物語は長編アニメーションの必要条件ではない。それは、山村さんの長編アニメーション『幾多の北』を観ても明らかです。
山村: 長年培われてきた映画の構造は、3部構成になっていたり、ターニングポイントがあったりと大体似たようなもので、アニメーション映画もそれに倣っているものが多いです。しかし、僕は長編アニメーションにおいて、構造の部分でこれまでのナラティブなパターンから抜け出す可能性があると考えています。
『Glass House』は9つの章に分かれていて、音楽でいう組曲のような形です。各章にタイトルがつけられ、それぞれが独立しているものと関連し合い、観客がその9つの章を繋ぎ合わせることで、1つの物語が見えてくるという構造です。一般的な映画の場合は、約15分の単位で1つの章がまとまり、それが3部構成で6パターンくらいの章が重なると長編映画になることがほとんどです。本作は40分なので長編と呼べるかどうかはわかりませんが、組曲的な9つの章から成り立つという点でその構造は非常に面白いと感じます。例えば、2フレーム単位で1つの絵があり、サブリミナルが永遠に続く2時間の映画なども面白いだろうと思います。
実は現在、1分の物語を90本繋げて90分の映画を作るという長編シナリオに取り組んでいます。この映画では、90本のショートフィルムは一見全く脈絡がないように感じられますが、それらを繋げることで何かが見えるかもしれない。このような構造における実験を試みたいと思っています。
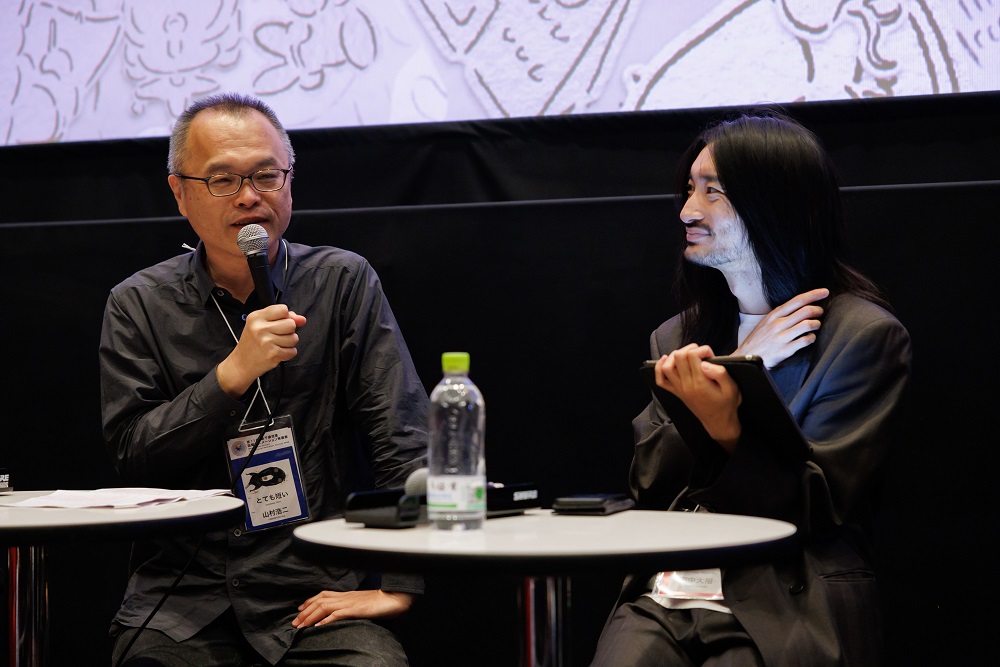
田中:本作はAI生成イメージとハンドドローイングのハイブリッド作品です。その点も評価が分かれるポイントかと思います。山村さんは「ひろしまアニメーションシーズン(HAS)」のアーティスティックディレクターとして上映作品の選考も行なっていますが、そこでは生成AIを導入した作品も選ばれていましたね。生成AIに対する山村さんの考えを教えてください。
山村:この作品は恐らく、CGIが使われていたり、マイブリッジのソースが見える写真があったり、何かの映画をベースにしてAIで加工したショットも使われていたり、様々な技法をハイブリッドした作品だと思います。AIは異なる要素を混ぜて新たなイメージや動きを作り出すことに非常に長けており、自分自身の素材をそこに加えることで、オリジナリティを生み出すための道具になるのではないかと感じています。
HASの選考でも、明らかにAIを使っている作品を2本選びました。AIが使われている作品は現代のアニメーションにおける通過点として重要だと思い選考に入れましたが、審査員の方々はあまり評価していないように感じました。「こんなの2分で作れるよね」といった反応があり、手作業を尊重しすぎる傾向があるのを感じました。
ボリス・ラべの『Rhizome』という作品が文化庁メディア芸術祭に応募された際にも、私は審査員を務めていたのですが、その時の審査会では誰一人としてこの作品に触れなかったんです。恐らく、コンピュータで簡単に作られたものだろうという印象を持っていたのでしょう。しかし、全部手書きの素材で制作されていることを僕が説明すると評価が一変し、その作品が大賞を受賞することになりました。今後生成AIについて考えていくにあたっても、アニメーション業界にある「手作りがすごい」という価値観は払拭したいと個人的には思っています。

田中:どれだけ手を動かしたかだけでアニメーションを評価すべきでないとしたら、では作品を評価するにあたって、いったい何が問われるべきだと思われますか?
山村: これは本当に難しい問題ですが、アーティストがどのような視点で、どのような試みをしようとしているのか、そしてそこに新しい発見がある作品が面白いと思います。特に映画祭という場では、既存の技術を使ったウェルメイドな作品を高く評価するよりも、私はもう少し外れた次の可能性を感じさせる作品を見つけたいし、評価したい。自分の価値観では追いつけないような作品に面白さを感じます。
田中:本作における生成AIの使われ方を、どうご覧になりましたか?
山村:本作で一番重要なモチーフになっているガラスの質感、フィクションの中での光の屈折を表現するためにAIが活用されています。また、この映画自体が引用の嵐であり、素材自体も引用が多いため、それらをスムーズにつなげる道具としてAIは最適だったと思います。ボリス・ラべは、アニメーション的な考え方を持っています。アニメーションが中割りや異なるイメージを繋ぐ力を持つのと同様に、AIもメタモルフォーゼとして異なるイメージを滑らかに繋げていくことが得意です。世の中にあるAI映像もモーフィング、つまり形が変化していくものが多く、それはアニメーションの黎明期に似ていると感じています。
田中:生成AIを含め、アニメーションにおける手法というのは「個別言語」に近いように感じます。それぞれの手法には固有の文法(syntax)があり、その範囲内でアーティストは独自の文体を練り上げていく。そういうふうにアニメーションという芸術を図式化できるかもしれないと思う時があります。山村さんはどう思いますか?
山村: その質問に100%同意できない部分もありつつ、逆に田中さんの意図をお聞きしたいところです。syntaxという部分で言うと、アニメーションは絵を動かすために非常に多くの方法が試されてきました。アニメーション技法は、動きをビジュアル上で作るための創意工夫の中から生まれてきたものであり、僕にとってはそれぞれが一種の「方言」のようなものに感じられます。例えば、切り紙っぽい方言があったり、AIっぽい方言があったりというように。
田中:それは、山村さんのアニメーションへの向き合い方が異質だからな気もします。おそらくボリス・ラべもそうですね。どういうことかというと、山村さんもボリス・ラべも様々な手法に取り組まれていますが、一般的にアニメーションのアーティストというのは、ストップモーションやハンドドローイング、コラージュなど、それぞれにシグネチャーな手法を有しているように思います。したがって手法は単なる「方言」のレベルにとどまらず、むしろ、アーティストにとって決定的な枠組みなのではないかと。
山村: 確かに、僕もボリス・ラべも同じような考えを持っていると思いますが、作品ごとに目指すものがあって、それに適した手法や物語構造をゼロから考えがちなタイプなので、ピンとこないのかもしれませんね。アニメーションの場合は非常に職人的な要素が強く、切り紙なら切り紙を一生追求しなければ極めることはできませんし、ハンドドローイングも同様に一生追求していかないと一定のレベルには到達しないという考え方があります。そうなると、一人で多くの技法を開発していくのは難しく、さらに現代ではAIが登場したことで、プログラミングのスキルがなければオリジナルの作品にはたどり着けない。工学的な発想を持たなければ、現代におけるオリジナルな文体を作れない時代に差し掛かっているかなと思います。
田中:少しズレるかもしれませんが、ソフトウェアやツールも表現をある種、言語のように規定しているように感じる時があります。
山村:その点にはとても共感します。選考で何千本ものフィルムを見ていると、あるソフトウェアが流通すると、そのソフトウェアの癖に合わせた作品が山ほど作られるようになり、それを抜ける作品が少ない。観る側としては、「もう少し工夫できないかな」とげんなりしてしまうんですよね。もちろん良い面もあって、例えばDragonframeの普及で、以前は職人にしかできなかった立体作品が、かなり多くの人がスムーズに制作できるようになってストップモーションが活性化し、手描きに必要だった難しいブラシのテクニックがアプリケーションによって補強・補助されるようになりました。ただ、作品のテイストがどれも似通ってしまう部分があり、違う使い方ができないものかともどかしい感じがします。
田中:例えば、絵画における平面性や彫刻における量感を追求する純粋化のベクトルがありますよね? 同じように手法やソフトウェア、ツールの限界を追求することが、アニメーション芸術の純粋化と考えることができるかもしれません。
山村:アニメーション自体が持つ問題だと思うんですが、アートフォームとしてのアニメーションの考え方もあれば、映画の一ジャンルとして、技法としてのアニメーションという考え方もあります。当然多くのアニメーションはエンターテイメントや娯楽、実用のために作られることが多いですよね。アートフォームとしてアニメーションの純粋さを追求するようなアーティストは限られており、実際、多くのアニメーションは産業、または工芸としての追求の方向に傾いてしまいます。
田中さんがおっしゃっている、純粋な芸術性としてのアニメーションの話は理解できますし、僕自身もアニメーションの本質や、他のメディアにはないアニメーションの純粋な形を追求したいと感じています。その可能性がどこかの作家や技術によって見つかるかもしれません。マクラーレンがカメラを使わずにフィルムに絵を描いたように、アニメーションにおける内的なイメージをどう映像としてビジュアル化するか。その過程で新しい技法や発想が生まれ、それがアニメーションの純粋な形として成り立つ可能性もあるのではないかと思います。
田中:「アニメーション」という言葉の中にはジャンルと芸術形式という似て非なる意味が共存しているということですね。言い換えれば、アニメーションにはある種の不純性がつきまとっている。山村さんやボリス・ラべは、アニメーションの不純さを前提としたうえで、それでもなお、創意工夫しながらアニメーションの純粋性を探求しているアーティストと言えるかもしれないですね。
山村:大変光栄な言葉で、ありがたいと思います。
田中:ところで今思い出したのですが、山村さんはかつて「Animations」というコレクティブを運営していましたが、その「Animations」の座談会で、細部は違うかもしれないのですが、「本当の意味でのクリエーションをCGで行うためにはプログラミングからやらないといけない」という旨の発言をされていたと記憶しています(編集者注:当該座談会は以下。「ライアン・ラーキンと『ライアン』 Animations座談会(前編)」(2007)。当トークイベントの内容をより深く理解するための補助線として参照されたい。座談会からすでに15年以上経過しているため、各参加者の考え方も当時とは変化していると推察されるが、生成AIの急速な拡大を受け、「アニメーションの本質」が再び問い直されている現在、ここで行われているCGに関する議論は、アニメーションとデジタル技術の関係を再考するうえで有益な示唆を与えてくれる)。今日の議論に通じる論点だと思います。
山村:そうですね。今後はプログラミングができないと新しい創作に向かえない時代になったかなと思います。僕がCGに手を出しづらいのは、自分でプログラミングができれば思い通りのものを作れると思うのですが、既存のアプリケーションを使って作ったものには満足できない部分があるからです。最近、初めてVRの制作をした際にCGを使いましたが、その不自由さを強く実感しました。
田中:このトークのテーマは「手法から考える」でしたが、むしろ、「文法を考える」という方が山村さんのアニメーション観に近いかもしれませんね。
山村:順番としては、そういうことだと思います。僕の場合、構造やナラティブの方法、文法への興味があって、そこへの実験性を求めています。具体的なものが決まった後に、アニメーションの手法やスタイルを探るという流れです。アニメーション制作や絵本制作においても、テキストやストーリーごとに道具や手法を変えるという方法を取ってきました。別に意図的にやっているわけではなくて、自然にそうなってしまう部分もありますが、順番としては手法や技法が後からついてくる感じですね。
田中:些細な点で恐縮ですが、「意図的にやっていない」というのは、無意識ということなのか、それとも意図することそれ自体が身体化したような感覚なのか、どちらなのでしょうか?
山村:その中間的な感じですね。僕はインスピレーション型の人間で、いきなりアイディアを思いついて何かを作りたくなる。モチベーションが急に上がって、それがどんな方法でどううまくいくのかもわからないまま創作が始まる。それが意識化されているのか無意識化されているのかで言うと、無意識化の方が近いと思います。直感型で、熟考型ではないんです。最近、脳科学の本をよく読んでいるのですが、直感というのは本質を見抜く力があるんですね。何万種類ある植物の中から、昔は科学的な方法がなくても「この草が病気に効く」といったことを勘で見つけてきて、最近科学が発展してようやくその薬の意味がわかるというようなことがあります。創作の中でも、そういった本質をつかむ直感力が非常に重要だと思います。その後に少しずつ考え始めて実行して、意識化することで必要なものがわかってきます。

田中:先程も少し話題に出ましたが、山村さんは最近ではVRにも取り組まれていますね。新しい技術は山村さんにインスピレーションを与え続けてくれますか?
山村:VRの作品を作った際、アニメーションの「見えていない部分」が見えたんですね。VRはフレームがなくて、360度が映像になります。フレームは元々カメラから来ていて、世界を切り取るものですが、実際にはフレームの外にも世界が広がっています。イマジネーションの世界にはフレームがないわけで、VRの方がより純粋なアニメーションに近いかもしれませんね。
また、モンタージュも使いづらいですね。360度の世界が急に変わってしまうので、映画的なモンタージュで文法を語る映像表現が難しくなります。アニメーションが当たり前のようにカット割りをしているのは、やっぱり映画的な文法に従っているからなんですね。改めてそのことに気づいたりもしました。
以前からモンタージュは比較的避けていて、ワンシーン・ワンカットで流れるような作品は『サティの「パラード」』からです。そして、今回『とても短い』では非常に短いワンショットで描き続けるという、映画的なカメラから抜け出したアニメーションの可能性に、VR作品の制作を経験して初めて気づき、それを言語化できるようになったという感じです。
田中:アニメーション映画祭は今後、新しい技術といかに向き合っていくべきだと思われますか?
山村:アニメーションフェスティバルと名乗っている限り、アニメーションから外れる作品をどう考えるかは、やはり問題になると思うんですね。映画祭だったら何でもありという部分もありますが、カテゴリーが限られたフェスティバルだからこそ、アニメーションとは何かを常に考え、アニメーションの可能性を見つけていけるのだと思います。実際に、HASでは「これはアニメーションではないな」と思うような、完全に実写的なAIによる作品もありました。そのような作品をどう考えるのかを常に問題提起し続けることが映画祭の役割だと思います。そして、その答えは観客の中にあると思います。